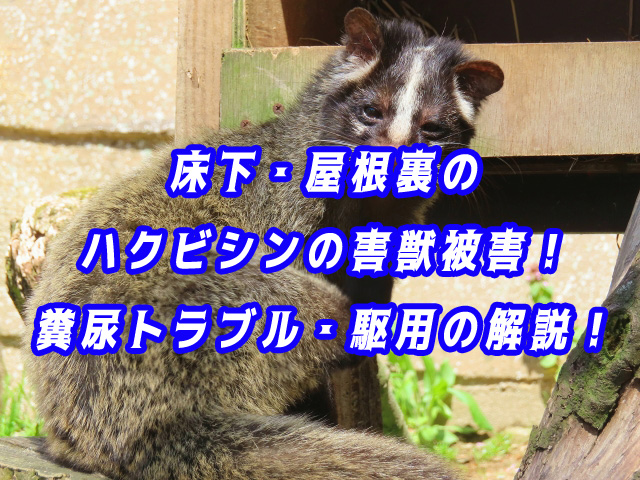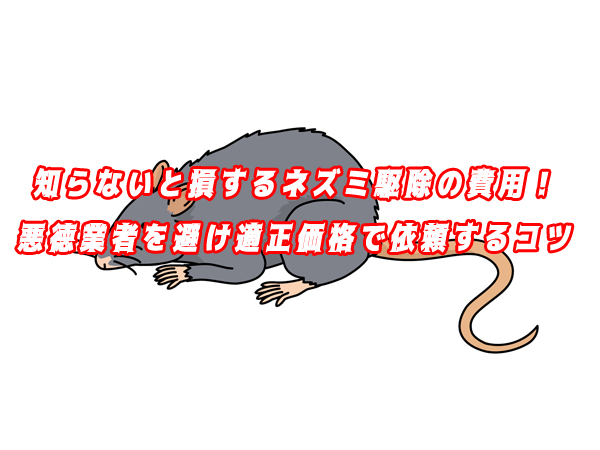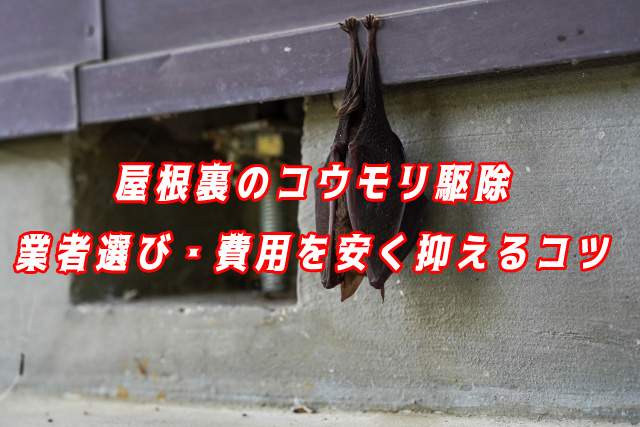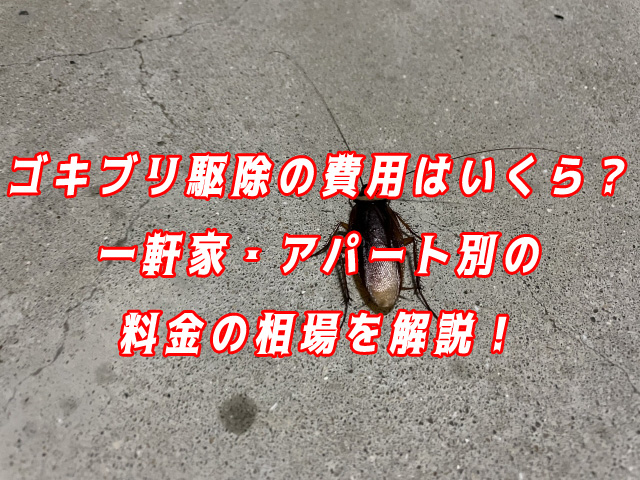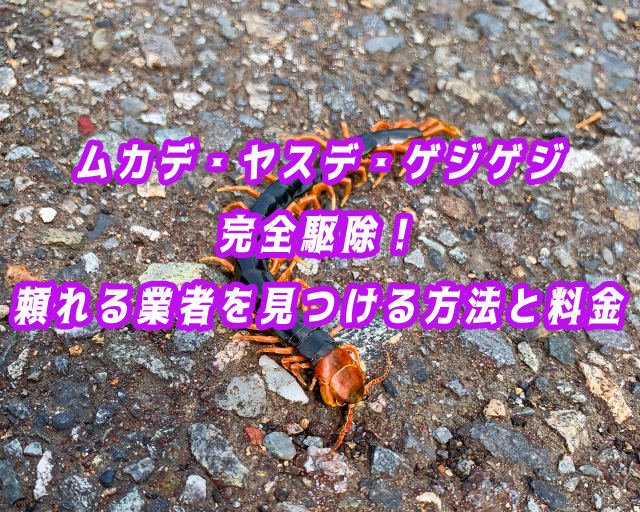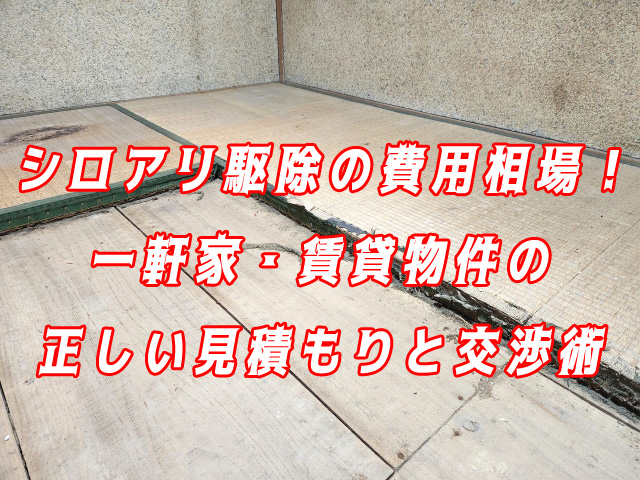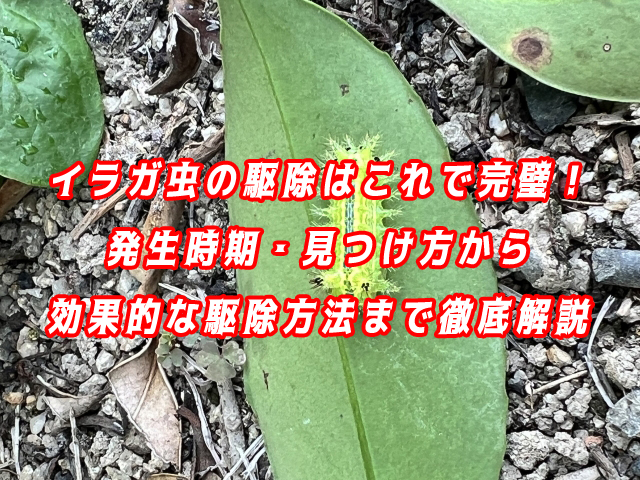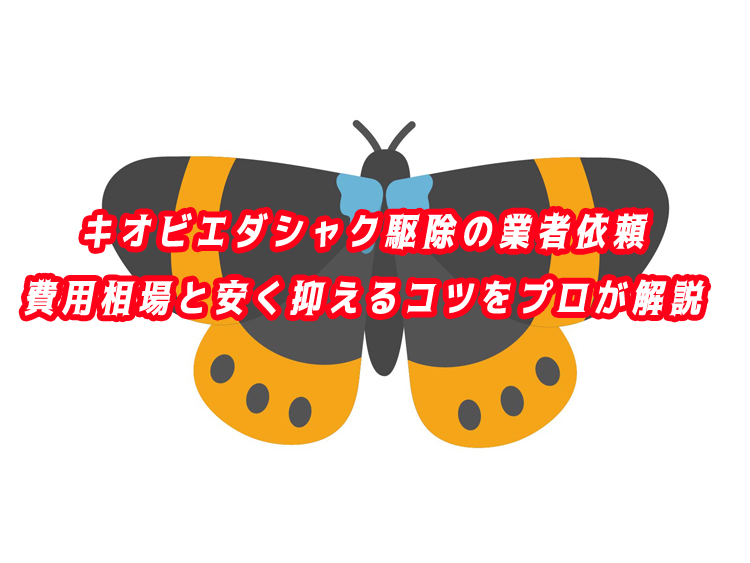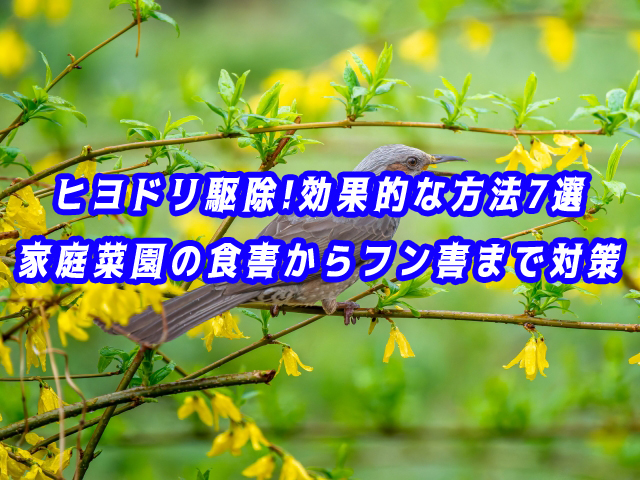
家庭菜園の大切な野菜がヒヨドリに食べられたり、ベランダのフン害に悩まされたりしていませんか?実はヒヨドリは鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕獲や殺傷はできません。
この記事では、法律に触れずにできる効果的な駆除・撃退方法を7つ厳選して解説します。
ご家庭でできる対策から専門業者に依頼する際の費用相場、やってはいけないNG例まで、ヒヨドリ被害を解決するための知識を網羅。
この記事を読めば、安全かつ確実なヒヨドリ対策が分かります。
目次
ヒヨドリを駆除する前に知るべき鳥獣保護管理法
ヒヨドリによる家庭菜園の食害やフン害に悩まされ、「今すぐ駆除したい」とお考えかもしれません。
しかし、ヒヨドリの駆除を行う前には、必ず知っておかなければならない重要な法律があります。それが「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(通称:鳥獣保護管理法)です。
この法律を知らずに自己判断で駆除を行うと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
まずは、ヒヨドリと法律の関係について正しく理解し、安全かつ適切な対策を進めましょう。
ヒヨドリは法律で保護されている鳥
ヒヨドリは、都市部でもよく見かける身近な鳥ですが、実は鳥獣保護管理法によって保護されている「野生鳥獣」の一種です。
この法律は、鳥類または哺乳類に属する野生動物の保護と管理を目的としており、一部の例外(ドブネズミ、クマネズミなど)を除き、日本のほぼすべての野生鳥獣が対象となっています。
ヒヨドリは「害鳥」というイメージが強いかもしれませんが、生態系を構成する一員として、法律上は他の野鳥と同様に保護の対象となっているのです。
許可なく捕獲や殺傷をすると罰則の対象に
鳥獣保護管理法により、国や自治体からの許可なくヒヨドリを捕獲したり、傷つけたり、殺傷したりすることは固く禁じられています。
これには、成鳥だけでなく、ヒナや卵を採取・損傷させる行為も含まれます。
例えば、庭に作られた巣を勝手に撤去したり、罠を仕掛けて捕まえたりする行為は違法です。
もし無許可で捕獲や殺傷を行った場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性があります。
被害に困っているからといって、安易に手を出してしまうと法律違反となり、罰せられるリスクがあることを絶対に忘れないでください。
ヒヨドリを追い払う対策は法律上問題ない
「では、何も対策できないのか?」と不安に思うかもしれませんが、ご安心ください。
法律で禁止されているのは、あくまでヒヨドリを「捕獲」したり「殺傷」したりする行為です。
ヒヨドリを傷つけずに「追い払う」ための対策は、法律上何の問題もありません。
例えば、防鳥ネットを張って物理的に侵入を防いだり、CDや反射テープなどの光るものを設置して警戒させたり、忌避剤を使って寄せ付けなくしたりといった方法は、すべて合法的な対策です。
この記事で後ほど詳しく紹介する「自分でできる駆除・撃退方法」は、すべてこの「追い払う」ことを目的とした合法的なアプローチですので、安心して実践してください。
ヒヨドリによる主な被害と発生しやすい時期
「ヒーヨ、ヒーヨ」という甲高い鳴き声が特徴的なヒヨドリ。
かつては秋の渡り鳥でしたが、近年では都市部にも定着し、一年を通して見かけるようになりました。
愛らしい姿とは裏腹に、ヒヨドリは私たちの生活に深刻な被害をもたらすことがあります。
主な被害は「食害」「フン害」「騒音」の3つです。
ここでは、具体的にどのような被害があるのか、そして被害が特に発生しやすい時期について詳しく解説します。
家庭菜園や畑での深刻な食害
ヒヨドリによる被害で最も深刻なのが、家庭菜園や農作物の食害です。
ヒヨドリは雑食性ですが、特に甘いものや柔らかいものを好むため、丹精込めて育てた野菜や果物が格好の標的となります。
群れで飛来し、あっという間に作物を食べ尽くしてしまうことも少なくありません。
また、単に食べるだけでなく、くちばしで突いて傷つけるだけの「遊び食い」をすることもあり、商品価値を大きく損なう原因にもなっています。
ヒヨドリが好む野菜や果物
ヒヨドリは非常に多くの種類の作物を食害します。
特に被害に遭いやすい代表的な野菜や果物は以下の通りです。
- 野菜類:キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ハクサイ、コマツナなどのアブラナ科野菜の葉や新芽は特に好物です。また、完熟したトマトやナス、キュウリなども狙われます。
- 果物類:みかんなどの柑橘類、柿、イチゴ、ブルーベリー、サクランボ、ビワなど、糖度の高い果物は大好物です。収穫間際の最も美味しい時期を狙って食べられてしまうケースが多発します。
- その他:ツバキやサザンカなど、花の蜜や花びらを食べることもあります。
これらの作物を育てている場合は、特に厳重な対策が必要です。
農林水産省も鳥獣ごとの被害防止マニュアルを公開しており、対策の参考になります。
ベランダや住宅でのフン害と騒音
ヒヨドリの被害は農地だけに留まりません。
都市部の住宅街でも、フン害や騒音が問題となっています。
ヒヨドリは電線やアンテナ、ベランダの手すり、カーポートの屋根などを休憩場所として利用するため、その下に大量のフンを落とします。
洗濯物や布団が汚されるだけでなく、フンは酸性のため、建物の外壁や車の塗装を劣化させる原因にもなります。
また、衛生面でも決して良いものではありません。
さらに、特徴的な甲高い鳴き声による騒音被害も深刻です。
特に早朝から大きな声で鳴き続けるため、安眠を妨げられてストレスを感じる方も少なくありません。
群れで鳴き始めると、その騒音は一層大きなものとなります。
ヒヨドリ被害が集中する時期は冬から春
ヒヨドリによる被害は一年中発生する可能性がありますが、特に被害が集中するのは、エサが少なくなる冬から繁殖期を迎える春にかけて(11月~5月頃)です。
山間部では冬になると昆虫や木の実などのエサが減少するため、ヒヨドリはエサを求めて平野部や市街地へと移動してきます。
この時期、家庭菜園ではブロッコリーやキャベツなどの冬野菜が栽培されており、ヒヨドリにとって格好の食料となります。
春になると繁殖期を迎え、ヒナを育てるために多くの栄養を必要とします。
そのため食欲が旺盛になり、柑橘類や春野菜、イチゴなどを積極的に狙うようになります。
この時期に適切な対策を怠ると、収穫直前の作物が全滅してしまうといった壊滅的な被害につながる恐れがあります。
ヒヨドリの完全駆除なら専門業者がオススメ
ご自身でヒヨドリ対策を試みても効果が見られない、被害が広範囲に及んでいる、あるいは高所での作業が必要で危険といった場合には、鳥害対策の専門業者に依頼するのが最も確実で安全な選択肢です。
ヒヨドリは鳥獣保護管理法で守られているため、法律を遵守した適切な対応が求められます。
知識と経験が豊富な専門業者であれば、法律の範囲内で最も効果的な方法を提案・実行してくれます。
ヒヨドリ駆除を業者に依頼するメリットとデメリット
専門業者への依頼を検討する際には、メリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
【メリット】
- 確実性と即効性がある: プロの知見に基づき、被害状況や建物の構造に合わせた最適な対策を迅速に実施してくれます。ヒヨドリの習性を熟知しているため、再発防止策まで含めた根本的な解決が期待できます。
- 安全性と法令遵守: 高所や足場の悪い場所での作業も、専門的な技術と装備で安全に行います。また、鳥獣保護管理法を遵守した適法な方法で駆除・対策を行うため、法的なトラブルに巻き込まれる心配がありません。
- 手間と時間の節約: 自分で対策グッズを探して購入したり、試行錯誤を繰り返したりする時間と労力を大幅に削減できます。
- 被害箇所の清掃・消毒まで任せられる: ヒヨドリのフンは、悪臭や建物の腐食だけでなく、感染症の原因となる病原菌を含んでいる可能性があります。専門業者なら、追い払い作業後のフンの清掃や、専門的な薬剤を使った消毒・殺菌作業まで一貫して依頼できます。
【デメリット】
- 費用がかかる: 当然ながら、自分で対策するよりも費用が発生します。被害の規模や対策内容によっては、高額になるケースもあります。
- 業者選びの手間がかかる: 数多くの業者の中から、信頼できる一社を見つけ出す必要があります。中には高額な請求をしたり、ずさんな作業をしたりする悪質な業者も存在するため、慎重な選定が求められます。
専門業者の駆除費用相場
ヒヨドリ駆除を業者に依頼する際の費用は、被害の状況、建物の種類(戸建て、マンションなど)、対策を施す範囲、作業の難易度によって大きく変動します。
以下に示すのはあくまで一般的な目安として参考にしてください。
- 現地調査・見積もり: 無料~10,000円程度(多くの業者が無料で行っています)
- 追い払い・忌避剤設置(ベランダなど小規模): 20,000円~50,000円程度
- 防鳥ネット設置(ベランダ一面): 30,000円~80,000円程度
- 広範囲の対策(家全体・畑・果樹園など): 100,000円~数十万円
- フンの清掃・消毒作業: 15,000円~(範囲や量による)
正確な料金を知るためには、必ず複数の業者から相見積もりを取り、作業内容と料金を比較検討することが不可欠です。
見積もりの内訳が不明瞭な場合は、詳細な説明を求めましょう。
信頼できる駆除業者の選び方
安心してヒヨドリ駆除を任せられる、優良な専門業者を選ぶためのチェックポイントを解説します。
- 実績と専門性: ヒヨドリを含む鳥害対策の実績が豊富か、ウェブサイトの施工事例などで確認しましょう。鳥の生態に関する専門知識を持っているかどうかも重要です。
- 明確な見積もり: 作業内容の内訳が詳細に記載された、分かりやすい見積書を提示してくれるかを確認します。「一式」などの曖昧な表記ではなく、「作業費」「材料費」「出張費」などが明確に分けられている業者が信頼できます。追加料金が発生する条件についても、事前に確認しておきましょう。
- 丁寧な現地調査: 電話やメールだけで判断せず、必ず現地を訪れて被害状況を詳細に調査してくれる業者を選びましょう。建物の構造や周辺環境を把握しなければ、最適な対策は提案できません。
- 保証制度の有無: 施工後にヒヨドリ被害が再発した場合に備え、保証制度を設けているかを確認します。保証期間や保証内容(無料での再施工など)を契約前に書面で確認することが大切です。
- 損害保険への加入: 万が一、作業中に建物や物品を破損してしまった場合に備え、損害賠償保険に加入している業者を選ぶとより安心です。
- 担当者の対応: 問い合わせや現地調査の際に、こちらの質問に丁寧に答え、親身に相談に乗ってくれるかなど、担当者の人柄や対応の質も重要な判断材料になります。
- 許可や資格: ヒヨドリの捕獲や卵・巣の撤去には、原則として行政の許可が必要です。こうした手続きの代行やアドバイスができるかどうかも、業者の専門性を見極めるポイントになります。害獣・害鳥駆除に関する業界団体、例えば公益社団法人日本ペストコントロール協会などに加盟しているかも一つの目安になります。
これらのポイントを踏まえ、複数の業者を比較検討し、納得のいく業者に依頼することが、ヒヨドリ被害解決への近道です。
【自分でできる】ヒヨドリの駆除・撃退に効果的な方法7選
専門業者に依頼する前に、まずは自分でできる対策から試したいという方も多いでしょう。
ヒヨドリは警戒心が強い一方、学習能力も高いため、複数の対策を組み合わせることが成功の鍵です。
ここでは、ご家庭で手軽に始められる効果的なヒヨドリ撃退法を7つ、具体的なポイントと合わせてご紹介します。
方法1 防鳥ネットやテグスで物理的に侵入を防ぐ
ヒヨドリ対策として最も確実で効果が高いのが、防鳥ネットやテグス(防鳥糸)を使って物理的に侵入経路を塞ぐ方法です。
一度設置すれば継続的な効果が期待でき、ヒヨドリに作物を食べられる心配を根本から断つことができます。
家庭菜園やベランダなど、守りたい場所が明確な場合に特に有効です。
防鳥ネットを設置する際のポイント
防鳥ネットは、ヒヨドリの侵入を物理的に防ぐための最も基本的なアイテムです。
正しく設置すれば、ほぼ100%の確率で被害を防ぐことができます。
- 網目のサイズを選ぶ:ヒヨドリの体長は約27.5cmですが、頭さえ入らなければ侵入できません。そのため、網目のサイズは20mm~30mm角のものを選びましょう。これより大きいと隙間から侵入される可能性があり、小さすぎると蝶などの益虫まで妨げてしまうことがあります。
- 隙間なく完全に覆う:ヒヨドリは賢く、わずかな隙間も見逃しません。ネットの裾がめくれたり、支柱との間に隙間が生まれたりしないよう、U字ピンや重し(石やレンガなど)を使って地面にしっかりと固定しましょう。作物全体をトンネル状やハウス状に完全に覆うのが理想的です。
- 作物とネットの間に空間を作る:ネットが作物に直接触れていると、ヒヨドリはその上からくちばしで突いてしまいます。支柱を立ててネットを高く張り、作物とネットの間に十分な空間を確保してください。
テグス(防鳥糸)の効果的な張り方
テグス(釣り糸のような細い糸)は、ヒヨドリが飛来した際に、見えにくい糸が羽に触れる不快感を利用して追い払う方法です。
ネットを張るのが難しい場所や、景観をあまり損ねたくない場合におすすめです。
キラキラと光るラメ入りのテグスは、光の反射効果も加わり、より高い撃退効果が期待できます。
- 畑や花壇の場合:作物の周囲に1~2m間隔で支柱を立て、地面から20cm程度の間隔で数段にわたって平行に張ります。上からの侵入も防ぐため、支柱の上部にも格子状にテグスを張り巡らせると万全です。
- ベランダの場合:手すりの上や、ヒヨドリがよく止まる場所に、数cm間隔で数本張るだけで効果があります。手すりの内側と外側に高さを変えて張ると、より止まりにくくなります。
方法2 CDや反射テープなど光るものを設置する
ヒヨドリをはじめとする多くの鳥は、強い光や不規則な光の反射を嫌う習性があります。
この習性を利用し、太陽光を乱反射させるアイテムを設置するのは、手軽でコストもかからない有効な対策の一つです。
- CDやDVDを吊るす:不要になったCDやDVDに穴を開け、紐で吊るします。風で揺れて回転することで、様々な角度に光を反射し、ヒヨドリを警戒させます。複数枚を連結して吊るすと、より効果が高まります。
- 防鳥テープ(キラキラテープ)を張る:銀色や赤銀色などのホログラム加工がされたテープを、畑の周りに張り巡らせます。風で「バタバタ」という音が出るタイプもあり、光と音の両方でヒヨドリを威嚇できます。テープを張る際は、少しねじりながら張ると、風を受けたときにより複雑な動きと光の反射が生まれます。
ただし、これらの光り物は、ヒヨドリが「害がない」と学習してしまうと効果が薄れる「慣れ」が生じやすいのが欠点です。
効果を持続させるためには、設置場所を定期的に変えるなどの工夫が必要です。
また、近隣住宅に光が反射して迷惑にならないよう、設置角度には配慮しましょう。
方法3 目玉風船やフクロウの置物で天敵がいると錯覚させる
ヒヨドリの天敵は、タカやフクロウといった猛禽類です。
その天敵がいるように見せかけて、恐怖心から近寄らせないようにするのも効果的な方法です。
特に、大きな目玉模様は鳥類に恐怖感を与える効果があると言われています。
- 目玉風船:猛禽類の目を模した、黄色や黒の大きな目玉模様が描かれたビニール製の風船です。風で不規則に揺れることで、ヒヨドリに「生きている天敵に見られている」と錯覚させます。
- フクロウの置物:畑や庭、ベランダにフクロウの置物を設置します。より効果を高めるためには、首が風で動くタイプや、センサーで音が鳴るタイプなどがおすすめです。
この方法も光り物と同様に、同じ場所に長期間設置したままだと、ヒヨドリに置物だと見破られてしまいます。
効果を持続させるには、時々設置場所を移動させたり、他の対策と組み合わせたりすることが重要です。
方法4 ヒヨドリが嫌がる音や超音波を利用した駆除グッズ
ヒヨドリの聴覚に訴えかけて追い払う方法もあります。
ただし、音を出す装置は近隣への配慮が不可欠なため、使用環境をよく考えてから導入しましょう。
- 忌避音:ヒヨドリの天敵であるタカの鳴き声や、銃声、爆発音などを再生する装置があります。ヒヨドリが飛来しやすい時間帯にタイマーで再生することで、危険な場所だと認識させます。ただし、住宅密集地での使用は騒音トラブルの原因となるため、周囲に民家がない農地などに適しています。
- 超音波発生装置:人間にはほとんど聞こえないが、鳥にとっては不快な周波数の超音波を発生させる装置です。ソーラー充電式で配線不要の製品も多く、手軽に設置できます。ただし、超音波の効果については個体差があるとも言われており、ペット(特に犬や猫)が嫌がる可能性もあるため注意が必要です。
方法5 固形やスプレータイプの忌避剤で寄せ付けない
鳥が嫌がる味覚、嗅覚、触覚を利用した忌避剤を使う方法です。
ヒヨドリがよく止まる場所や、被害に遭っている植物の近くに使用することで、その場所を「不快な場所」と学習させ、寄り付かなくさせる効果が期待できます。
- スプレータイプ:カプサイシン(唐辛子成分)や木酢液など、鳥が嫌う天然由来成分のスプレーを、ベランダの手すりや物干し竿、作物の葉などに直接吹き付けます。手軽ですが雨で流れやすいため、定期的な散布が必要です。
- 固形・ジェルタイプ:鳥が嫌うニオイを発する固形物をネットに入れて吊るしたり、ベタベタとした不快な感触のジェルを手すりなどに塗布したりします。スプレータイプよりも効果の持続期間が長いのが特徴です。
忌避剤を使用する際は、必ず商品説明をよく読み、用途に合ったものを選びましょう。
特に家庭菜園などで使用する場合は、農作物に使用しても安全な成分かを確認することが非常に重要です。
方法6 頻繁な見回りでヒヨドリに危険な場所と認識させる
非常にシンプルですが、人の気配を感じさせることが有効な対策になります。
ヒヨドリは警戒心が強いため、頻繁に人が現れる場所を「安全な餌場ではない」と判断し、次第に寄り付かなくなります。
- 庭仕事や水やりなどで、畑や庭に出る回数を増やす。
- ヒヨドリを見かけたら、すぐにその場に行き、手を叩いたり大きな声を出したりして追い払う。
- 犬を飼っている場合は、庭で遊ばせるだけでも効果が期待できます。
この方法は根気が必要ですが、他の対策と組み合わせることで相乗効果が生まれます。
例えば、防鳥テープを設置した上で頻繁に見回りをすれば、ヒヨドリはより強い警戒心を抱くようになります。
方法7 餌になるものを撤去し餌場にさせない
ヒヨドリがあなたの家にやってくる最大の理由は、そこに「餌」があるからです。
他の対策をどれだけ行っても、魅力的な餌が豊富にあれば、ヒヨドリは危険を冒してでも飛来しようとします。
餌場にさせないための環境づくりは、すべての対策の基本となります。
- 家庭菜園・果樹:熟した野菜や果物は、ヒヨドリにとって格好のごちそうです。収穫時期を逃さず、早めに収穫しましょう。傷んで地面に落ちた実なども、放置せずに速やかに片付けてください。
- 生ゴミ:生ゴミの管理も重要です。ゴミ出しの日まで屋外に置く場合は、蓋つきのゴミ箱に入れるか、カラス対策と同様にゴミネットで完全に覆い、ヒヨドリが漁れないようにしましょう。
- その他:屋外で飼っているペットの餌の食べ残しなども、ヒヨドリの餌になってしまう可能性があります。こまめに片付けるように心がけましょう。
これらの対策は、ヒヨドリだけでなく、カラスや他の害鳥対策にも共通する重要なポイントです。
農林水産省も鳥獣被害対策の基本として、餌場の除去を推奨しています。
【場所別】家庭でできるヒヨドリ対策の具体例
ヒヨドリによる被害は、家庭菜園、ベランダ、庭の果樹など、場所によって内容が異なります。
そのため、それぞれの状況に合わせた対策を講じることが重要です。
ここでは、場所別に家庭でできる効果的なヒヨドリ対策の具体例を詳しく解説します。
家庭菜園や畑のヒヨドリ対策
家庭菜園や畑は、ヒヨドリにとって格好の餌場です。
特に、キャベツやブロッコリーなどの葉物野菜、完熟したトマトなどは大きな食害を受けやすいでしょう。
作物を守るためには、物理的にヒヨドリの侵入を防ぐ方法が最も確実です。
最も効果的な対策は、作物全体を「防鳥ネット」で覆うことです。
ヒヨドリが侵入できないよう、網目のサイズは20mm~30mm角程度のものを選びましょう。
設置する際は、トンネル支柱などを利用してネットと作物の間に十分な空間を作ることがポイントです。
ネットが作物に密着していると、外からくちばしでついばまれてしまう可能性があります。
また、ヒヨドリは地面のわずかな隙間からも侵入するため、ネットの裾はU字ピンや土、レンガなどでしっかりと固定してください。
畑全体をネットで覆うのが難しい場合は、「テグス(防鳥糸)」を張り巡らせる方法も有効です。
作物の周囲や上空に、高さや間隔を変えながら複数本設置します。
ヒヨドリが飛来した際に、見えにくいテグスが羽に触れることを嫌がり、その場所を危険だと認識して近寄らなくなります。
キラキラと光を反射するタイプのテグスは、威嚇効果も期待できるためおすすめです。
これらの物理的な対策と並行して、CDや反射テープなどの光るものを吊るし、ヒヨドリを警戒させる方法を組み合わせると、より高い撃退効果が期待できます。
ベランダや庭のフン害対策
ベランダの手すりや物干し竿、庭のウッドデッキなどは、ヒヨドリの休憩場所や見張り場所になりやすく、フン害が集中するスポットです。
洗濯物が汚されたり、悪臭や衛生面の問題に悩まされたりするケースも少なくありません。
ベランダのフン害対策として最も確実なのは、ベランダ全体を「防鳥ネット」で覆うことです。
隙間なく設置すれば、ヒヨドリの侵入を完全に防ぐことができます。
景観を損ねにくい透明色のネットも市販されています。
手すりや室外機の上など、ヒヨドリがよくとまるピンポイントな場所には、「剣山(バードスパイク)」や「防鳥ワイヤー」の設置が効果的です。物理的にとまる場所をなくすことで、飛来を防ぎます。
鳥を傷つけにくいプラスチック製や樹脂製の製品を選ぶようにしましょう。
また、ヒヨドリが嫌がる臭いや成分を利用した「忌避剤」も有効です。
手すりなどに直接塗布するジェルタイプや、手軽に使えるスプレータイプがあります。効果の持続期間を確認し、雨などで流れた場合は再度塗布するなど、定期的なメンテナンスが必要です。
非常に重要なのが、フンのこまめな清掃です。鳥のフンは縄張りのマーキングの役割があり、放置すると「ここは安全な場所だ」と認識され、他のヒヨドリまで呼び寄せてしまいます。フンを見つけたらすぐに掃除しましょう。
その際、乾燥したフンを吸い込むと健康被害のリスクがあるため、マスクと手袋を着用し、水で湿らせてから拭き取るようにしてください。
掃除後はアルコールスプレーなどで消毒するとより衛生的です。
みかんなど果樹のヒヨドリ対策
庭で大切に育てているみかん、柿、びわ、ブルーベリーなどの果樹は、収穫前の甘くなった実がヒヨドリの標的になります。
せっかく実った果物を食べられてしまわないよう、収穫期が近づいたら早めに対策を講じましょう。
果樹の対策で最も効果が高いのは、家庭菜園と同様に「防鳥ネット」で木全体を覆う方法です。
木のサイズに合ったネットを用意し、下から侵入されないように裾を幹の部分でしっかりとしばるか、地面に固定します。
鳥が中の果実を食べられないよう、ネットが枝や果実に密着しすぎないように注意して設置してください。
木全体を覆うのが難しい場合や、特に守りたい果実だけを保護したい場合は、果実一つひとつに「袋がけ」をするのも確実な方法です。
手間はかかりますが、鳥による食害だけでなく、病害虫からも果実を守る効果があります。
これらの対策に加え、枝の間にテグスを張ったり、光るCDなどを吊るしたりすることで、ヒヨドリが木に近づきにくい環境を作ることができます。
また、熟した果実はヒヨドリを引き寄せる原因となるため、食べ頃になったものから早めに収穫することも重要な対策の一つです。
効果がない?やってはいけないNGなヒヨドリ駆除方法
ヒヨドリによる被害が深刻化すると、一刻も早く解決したいという焦りから、誤った方法に手を出してしまうことがあります。
しかし、効果がないばかりか、法律に違反したり、周囲に危険を及ぼしたりする方法も少なくありません。
ここでは、絶対にやってはいけないNGなヒヨドリ対策について、その理由とともに詳しく解説します。
ヒヨドリを傷つける罠の設置
ヒヨドリを直接捕獲したり傷つけたりする罠の設置は、絶対にやめてください。
これには、法律、安全性、効果のすべての面で大きな問題があります。
まず最も重要な点として、ヒヨドリは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」によって保護されている野生鳥獣です。
都道府県知事の許可なく野生のヒヨドリを捕獲・殺傷することは固く禁じられており、違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、かすみ網やトラバサミといった罠は、ヒヨドリだけでなく、他の野鳥やペット、さらには小さな子供が誤ってかかってしまう危険性もはらんでいます。周囲の安全を脅かす行為であり、絶対に使用してはいけません。
たとえ数羽を捕獲できたとしても、群れで行動するヒヨドリの被害を根本的に解決することは難しく、むしろ警戒心を強めてしまい、その後の対策をより困難にするだけです。
毒餌の使用や農薬の不適切な散布
毒餌(毒団子など)を設置してヒヨドリを駆除しようとする行為も、非常に危険なため厳禁です。
これも鳥獣保護管理法に違反する可能性が高いだけでなく、意図しない二次被害を引き起こすリスクが極めて高い方法です。
毒餌は、ヒヨドリ以外の鳥や動物が誤って食べてしまう可能性があります。
例えば、ペットの犬や猫、あるいは希少な野生動物が命を落とすといった悲劇につながりかねません。
また、毒を食べたヒヨドリを、タカなどの猛禽類や他の動物が捕食することで、毒が連鎖し、生態系全体に深刻な悪影響を及ぼす恐れがあります。
さらに、登録されていない農薬を鳥獣の駆除目的で使用したり、不適切な方法で散布したりすることも農薬取締法に違反します。
使用した毒物や農薬が土壌に残留し、家庭菜園で育てている野菜や果物を汚染してしまう危険性も考慮しなければなりません。
無許可での巣や卵の撤去
自宅の敷地内にヒヨドリが巣を作ってしまった場合、フン害や鳴き声に悩まされることがあります。
しかし、ヒナや卵がある巣を勝手に撤去することは、鳥獣保護管理法で禁止されています。
巣の中のヒナや卵も、親鳥と同様に法律で保護されているため、無許可で撤去(捕獲)すれば罰則の対象となります。
無理に巣を撤去しようとすると、親鳥が激しく威嚇してくることもあり危険です。
また、一度巣を撤去しても、ヒヨドリはその場所を安全な営巣場所と認識しているため、同じ場所やごく近くに再び巣を作ってしまう可能性が高く、根本的な解決にはなりません。
どうしても巣を撤去する必要がある場合は、絶対に自分で行わず、まずはお住まいの自治体の役所(環境課や農林水産課など)に相談してください。
専門の駆除業者を紹介してもらえたり、適切な手続きについてアドバイスを受けられたりします。
なお、ヒヨドリが巣立ち、巣の中にヒナや卵がいないことが確認できる「空の巣」であれば、許可なく撤去しても問題ありません。
まとめ
ヒヨドリは鳥獣保護管理法により保護されており、無許可での捕獲や殺傷は法律で禁止されています。
そのため、ヒヨドリ対策の基本は「追い払う」ことです。
この記事で紹介した防鳥ネットや忌避剤などの方法を試し、被害が深刻な場合や根本的な解決を望むなら、専門業者への相談が最も安全で確実な選択肢と言えます。
法律を遵守し、ご自身の状況に合った最適な対策を選び、大切な家庭菜園や住環境を守りましょう。