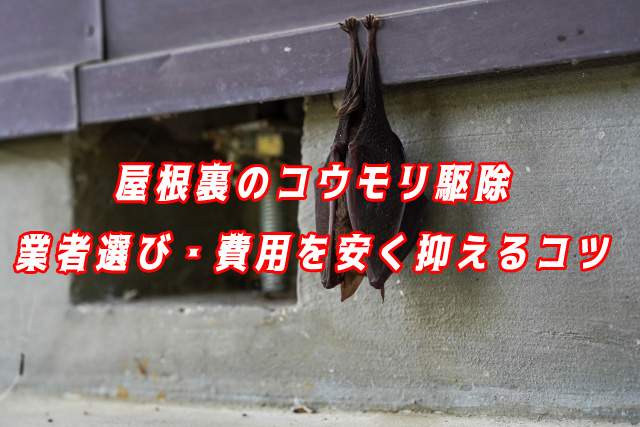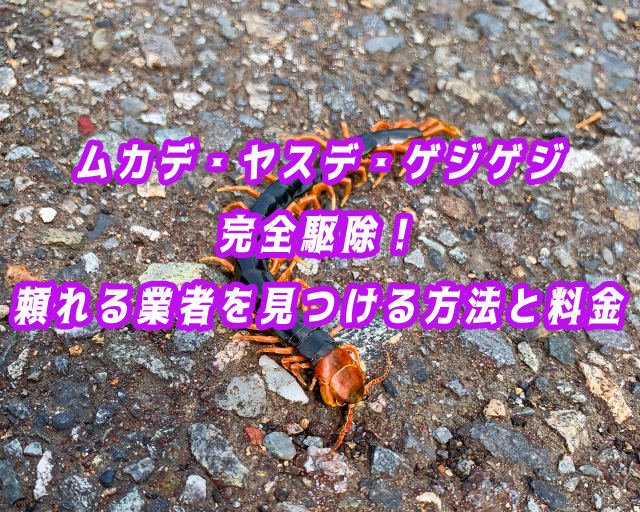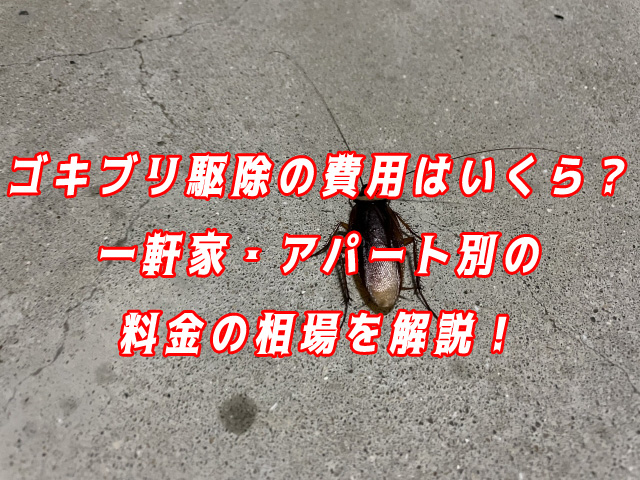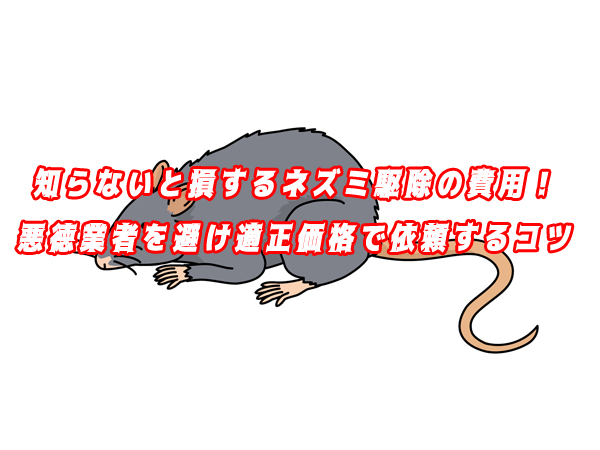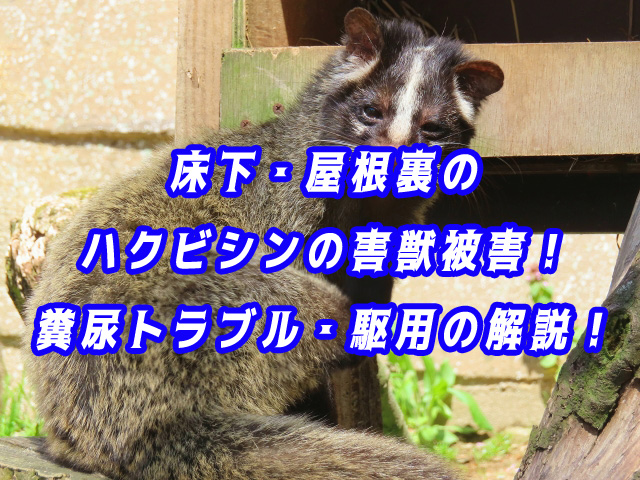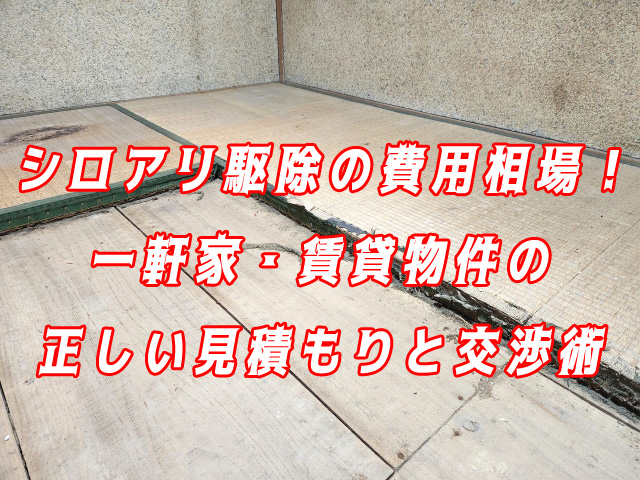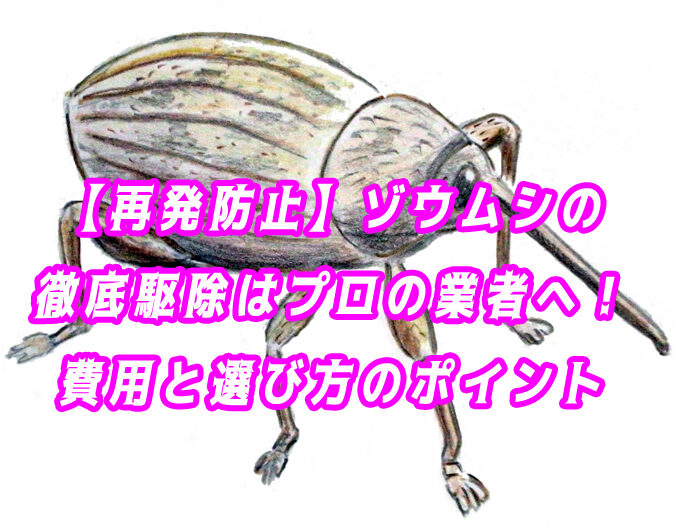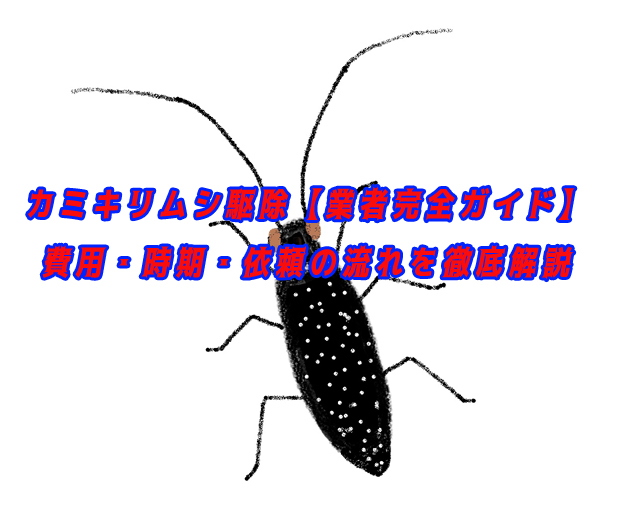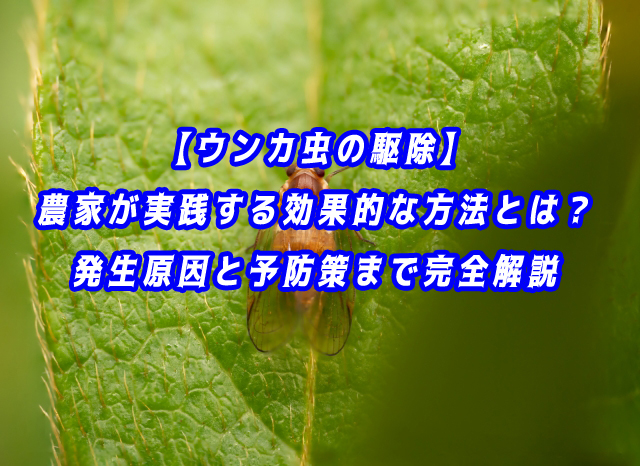
稲の大敵、ウンカ虫による坪枯れなどの被害にお困りではありませんか。
この記事では、ウンカの種類と発生原因から、農家が実践する農薬を使った確実な駆除方法、家庭菜園でも安心な対策までを徹底解説します。
ウンカ防除を成功させる鍵は、発生状況に応じた薬剤の適切な選択と散布タイミングの見極めです。
総合的な予防策を学び、大切な作物を深刻な被害から守りましょう。
もしかしてウンカ虫?まずは敵の正体と被害を知ろう
大切に育てている稲の株元に、小さな虫がびっしりと群がっているのを見つけたことはありませんか?あるいは、順調に育っていたはずの稲が急に黄色く変色し、元気がなくなってきた…。
もし、そんな兆候に心当たりがあれば、それは「ウンカ虫」の仕業かもしれません。
ウンカ虫は、日本の稲作において最も警戒すべき害虫の一つです。
まずは敵の正体を知り、その被害の深刻さを理解することが、効果的な駆除への第一歩となります。
ウンカ虫とはどんな害虫か
ウンカ虫とは、カメムシ目(半翅目)ウンカ科に属する昆虫の総称です。
体長はわずか3mm~5mm程度と非常に小さく、見た目はセミを極小にしたような形をしています。
この小さな害虫は、稲の茎や葉にストローのような鋭い口(口針)を突き刺し、養分を吸い取って生活する「吸汁性害虫」です。
ウンカ虫の最も恐ろしい特徴は、その驚異的な繁殖力にあります。
好条件が揃うと、短期間で爆発的に個体数が増殖し、あっという間に水田全体に被害が拡大する可能性があります。
そのため、発見が遅れると手遅れになりかねない、非常に厄介な害虫なのです。
放置は危険 ウンカ虫が引き起こす深刻な被害
ウンカ虫による被害は、単に稲の養分が吸われるだけではありません。
放置すると、収穫量の大幅な減少や米の品質低下に直結する、次のような深刻な被害を引き起こします。
- 直接的な吸汁被害と「坪枯れ」
ウンカ虫の集団による吸汁が続くと、稲は栄養を奪われて生育が著しく悪化し、葉が黄変・褐変してしまいます。被害が深刻化すると、水田の一部がまるで焼け焦げたかのように円形にまとまって枯れ上がる「坪枯れ(つぼがれ)」という特徴的な現象が発生します。坪枯れが起こると、その部分の稲は完全に枯死し、収穫は絶望的となります。 - ウイルス病の媒介
ウンカ虫は、吸汁の際にイネ縞葉枯病(いねしまはがれびょう)やイネ黒すじ萎縮病(いねくろすじいしゅくびょう)といった、稲にとって致命的なウイルス病を媒介します。一度ウイルス病に感染した稲は治療法がなく、生育不良や枯死に至るため、抜本的な対策が求められます。 - すす病の誘発
ウンカ虫の排泄物(甘露)は糖分を多く含んでおり、これを栄養源として「すす病」という黒いカビが発生することがあります。すす病が葉の表面を覆うと、光合成が妨げられ、稲のさらなる生育不良を招きます。
ウンカ虫の主な種類と見分け方
日本の水田で特に問題となるウンカ虫は、主に「トビイロウンカ」「セジロウンカ」「ヒメトビウンカ」の3種類です。
それぞれ生態や加害方法が異なるため、的確な防除を行うには、どの種類のウンカ虫が発生しているかを見分けることが重要です。
トビイロウンカとセジロウンカは、主に梅雨前線の気流に乗って海外から飛来する「飛来性害虫」として知られています。
トビイロウンカ
日本の稲作に最も大きな被害をもたらすウンカ虫です。
体長は約4.5mmで、翅(はね)を含めて全体的に褐色から黒褐色をしています。
最大の特長は、稲の「株元」に集中して寄生し、吸汁することです。
水田を見回る際は、稲の上部だけでなく、株元をかき分けて念入りに確認する必要があります。
高温・多湿を好み、7月中旬以降に飛来して秋に大発生することが多いため「秋ウンカ」とも呼ばれ、前述した「坪枯れ」を引き起こす主犯格です。
セジロウンカ
体長は約3mmとやや小型で、全体的に淡い黄緑色をしています。
名前の通り、成虫の背中の中央に白い菱形の紋があるのが見分けるための最も分かりやすいポイントです。
トビイロウンカが株元を好むのに対し、セジロウンカは稲の「中位~上位の葉」に寄生する傾向があります。
飛来時期は6月下旬から7月中旬とトビイロウンカより早く、イネ黒すじ萎縮病などを媒介することがあります。
ヒメトビウンカ
体長は約3.5mmで、黒褐色の体をしています。
他の2種との決定的な違いは、海外から飛来するのではなく、日本国内の雑草地などで成虫や幼虫の姿で「越冬」する点です。
春になると水田に移動し、田植え後の若い稲に寄生します。
直接的な吸汁被害よりも、深刻なウイルス病である「イネ縞葉枯病」を媒介するベクター(媒介者)として極めて危険視されています。
この病気に強い抵抗性を持つ品種の導入が、有効な対策の一つとなります。
なぜあなたの田畑に?ウンカ虫が大量発生する主な原因
ウンカ虫の被害に気づいた時、「なぜうちの田んぼにだけ?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。
ウンカ虫の発生は、単一の原因ではなく、飛来、栽培環境、気象条件という複数の要因が複雑に絡み合って起こります。
原因を正しく理解することが、効果的な駆除と来年に向けた予防策の第一歩です。
ここでは、ウンカ虫が大量発生する主な3つの原因を詳しく解説します。
海外からの飛来が主な発生源
日本の水田で問題となるトビイロウンカやセジロウンカは、実は日本国内で冬を越すことができません。
彼らは「飛来性害虫」と呼ばれ、毎年、梅雨の時期(6月下旬から7月中旬頃)に、中国大陸南部や東南アジアから、梅雨前線に伴う南西の風に乗って長距離を移動し、日本にやってきます。
つまり、ウンカの発生は、まず海外からの飛来がなければ始まりません。
その年の飛来数や飛来時期は、発生源となる海外での発生状況や、飛来時期の気流に大きく左右されます。
そのため、農林水産省や各都道府県が発表する病害虫発生予察情報を定期的に確認し、自分の地域への飛来リスクを把握しておくことが極めて重要です。
この情報を元に、初期防除のタイミングを計ることが被害を最小限に抑える鍵となります。
密植や窒素肥料の過剰な使用
ウンカ虫が海外から飛来したとしても、その後の増殖には田畑の環境が大きく影響します。
特に「密植」と「窒素肥料の過多」は、ウンカにとって非常に好都合な環境を作り出してしまいます。
稲を密植すると、株元まで日光が届きにくくなり、風通しも悪化します。
これにより、株元は常にジメジメとした多湿な環境になります。
ウンカはこのような高温多湿の環境を好み、活発に繁殖します。
また、風通しの悪さは、ウンカの天敵であるクモなどの活動を妨げることにも繋がり、結果的にウンカの天国となってしまうのです。
さらに、稲を元気に育てようと窒素肥料を過剰に与えることも逆効果です。
窒素分が多い稲は、葉の色が濃くなり、茎や葉が柔らかく育ちます。
ウンカは、このような柔らかく栄養価(特にアミノ酸)が高い稲を好んで吸汁し、産卵数も増加する傾向があります。
良かれと思って行った栽培管理が、知らず知らずのうちにウンカを呼び寄せ、大発生を招く原因となっているケースは少なくありません。
高温や梅雨明けの気候条件
飛来したウンカが水田に定着した後、その数を爆発的に増やす引き金となるのが気象条件です。
ウンカは高温を好み、特に気温が25℃以上になると発育スピードが速まり、世代交代のサイクルが短くなります。
1世代の期間が短くなることで、短期間のうちにネズミ算式に個体数が増加し、あっという間に坪枯れなどの深刻な被害を引き起こします。
特に注意が必要なのが、梅雨明け後の気候です。
梅雨が明けて高温で晴天の日が続くと、ウンカの活動は最も活発になります。
反対に、大雨や台風はウンカを稲から洗い流す効果があるため、雨が少ない「空梅雨」の年や、夏に雨が降らない日が続く場合は、ウンカの密度が急激に高まるリスクがあります。
日々の天気予報にも注意を払い、高温が続く予報が出た際には、より一層の警戒と圃場のこまめな観察が求められます。
プロが実践するウンカ虫の効果的な駆除方法
水稲をはじめとする作物に甚大な被害をもたらすウンカ虫。
一度大量発生してしまうと、その駆除は容易ではありません。
しかし、発生状況や時期に応じて適切な方法を選択することで、被害を最小限に食い止めることが可能です。
ここでは、多くの農家が実践している化学農薬を使った確実な駆除から、家庭菜園でも安心して取り組める方法まで、プロの視点でウンカ虫の効果的な駆除方法を詳しく解説します。
農薬を使った確実なウンカ虫駆除
大規模な水田などでウンカ虫が広範囲に発生した場合、農薬による化学的防除が最も現実的で効果的な手段となります。
ウンカ虫は増殖スピードが非常に速いため、発見が遅れると手遅れになることも少なくありません。
農薬を適切に使用し、迅速かつ確実に個体数を減少させることが、収穫量を守るための重要な鍵となります。
農薬の種類と選び方
ウンカ虫の駆除に使用される農薬には、様々な系統や剤形があります。
ウンカ虫は薬剤抵抗性を獲得しやすいため、同じ系統の農薬を連続して使用することは避けなければなりません。
作用性の異なる系統の農薬を順番に使用する「ローテーション散布」を心掛けることが、長く効果を維持する上で不可欠です。
農薬を選ぶ際は、主に以下の点を考慮します。
- 作用系統: ネオニコチノイド系、ジアミド系、ピリジン系など、異なる作用を持つ系統を組み合わせます。
- 対象のウンカ: トビイロウンカに高い効果を示すもの、セジロウンカに有効なものなど、薬剤によって得意な害虫が異なります。
- 使用時期: 田植え時の「箱処理剤」、生育期に散布する「粒剤(水面施用剤)」、緊急時に使用する「液剤(茎葉散布剤)」など、時期に応じた剤形を選びます。
代表的な農薬には「スタークル」「ダントツ」「プリンス」「チェス」などがあり、それぞれに粒剤や液剤といった異なる剤形が用意されています。
使用する際は、必ずラベルを確認し、対象作物や使用時期、希釈倍率などの使用基準を厳守してください。
どの農薬を選べばよいか迷った場合は、地域のJA(農協)や農業指導センターに相談することをおすすめします。
箱処理剤による初期防除
ウンカ虫対策の基本は、発生させない・増やさないことです。
そのために最も重要なのが、田植え時の育苗箱に施用する「箱処理剤」による初期防除です。
箱処理剤は、有効成分が稲の根から吸収され、効果が長期間(約60日〜90日)持続します。
これにより、海外から飛来してくる第一世代のウンカが稲に定着し、産卵・増殖することを防ぎます。
この初期防除を徹底することで、本田での農薬散布の回数を減らすことにも繋がり、労力とコストの削減にも貢献します。
代表的な箱処理剤には「アドマイヤー箱粒剤」や「プリンス粒剤」などがあります。
粒剤(水面施用剤)での中期防除
箱処理剤の効果が薄れてくる出穂期前後に、ウンカの発生が確認された場合や、多発生が予想される場合には、「粒剤(水面施用剤)」による中期防除を行います。
このタイプの農薬は、水田の水面に直接散布します。
薬剤の成分が水に溶け出し、稲の根から吸収されて稲全体に行き渡る「浸透移行性」という性質を持っています。
この性質により、薬剤が直接かかりにくい株元に潜んでいるウンカに対しても高い殺虫効果を発揮します。
散布作業が比較的容易な点もメリットです。「ダントツ粒剤」や「スタークル粒剤」などがこのタイプに該当します。
液剤(茎葉散布剤)での緊急駆除
圃場の観察を怠り、ウンカがすでに多発してしまった場合には、即効性のある「液剤(茎葉散布剤)」による緊急駆除が必要です。
動力噴霧器などを用いて、薬剤を水で希釈して稲の茎や葉に直接散布します。
ウンカは稲の株元に集中して生息しているため、ノズルの向きを工夫し、薬剤が株元までしっかりと届くように散布することが極めて重要です。
散布量が不十分だと、生き残った個体が再び増殖してしまうため、ムラなく丁寧に散布しましょう。
ただし、液剤散布は薬剤が風で飛散(ドリフト)しやすいため、風の強い日を避け、近隣の作物や住宅に影響が出ないよう細心の注意を払う必要があります。
農薬を散布する最適なタイミングと注意点
農薬による防除効果を最大限に引き出すには、散布するタイミングが非常に重要です。
タイミングを逃すと、効果が半減したり、手遅れになったりすることがあります。
散布の判断基準となるのが「要防除水準」です。
これは、経済的な被害を及ぼす害虫の密度を示す指標で、この水準を超える前に防除を行うのが基本です。
具体的なタイミングを知るためには、各都道府県の病害虫防除所などが発表する「病害虫発生予察情報」を定期的に確認することが不可欠です。
この情報には、ウンカの飛来状況や発生予測が示されており、防除の計画を立てる上で非常に役立ちます。
農薬散布時の注意点は以下の通りです。
- 天候の確認: 風の強い日や雨が予想される日は避け、晴天で風の穏やかな日を選びます。
- 時間帯の選択: 日中の高温時を避け、比較的涼しい早朝や夕方に行うのが一般的です。
- 安全装備の着用: 農薬散布時は、マスク、ゴーグル、長袖・長ズボン、手袋などの保護具を必ず着用し、薬剤を吸い込んだり皮膚に付着したりしないようにします。
- 使用基準の遵守: 農薬ラベルに記載されている使用回数、使用時期、希釈倍率などの基準を必ず守ってください。
家庭菜園でも安心 農薬に頼らないウンカ虫駆除
「自宅の庭やベランダで育てている野菜にウンカが付いてしまったが、化学農薬は使いたくない」という方も多いでしょう。
家庭菜園や小規模な栽培であれば、農薬に頼らない方法で対処することも可能です。
ただし、これらの方法は化学農薬ほどの即効性や確実性はないため、発生初期に根気強く続けることが大切です。
天敵(クモやカエル)を活かす生物的防除
自然界には、ウンカを捕食してくれる頼もしい天敵がたくさんいます。
田んぼや畑に生息するクモ類は、ウンカの最も有力な天敵です。
また、カエルやカマキリ、トンボなどもウンカを食べてくれます。
これらの天敵が住みやすい環境を整えることで、ウンカの異常発生を抑制できます。
むやみに殺虫剤を使用しない、あぜ草を適度に残すなど、多様な生物が共存できる環境づくりを心掛けましょう。
牛乳や木酢液を使った自然由来のスプレー
家庭で手軽に試せる方法として、牛乳や木酢液を水で薄めてスプレーする方法があります。
牛乳をスプレーすると、乾く際に膜ができてウンカの気門(呼吸するための穴)を塞ぎ、窒息させる効果が期待できると言われています。
木酢液は、植物の成長を助ける効果のほか、その独特の匂いによって害虫を寄せ付けにくくする忌避効果が期待されます。
どちらも発生初期の個体数が少ないうちにお試しください。効果が見られない場合は、他の方法と組み合わせる必要があります。
物理的に捕殺する方法
最も原始的ですが、確実な方法が物理的な駆除です。
ウンカが付いている葉や茎を見つけたら、手で直接取り除くか、テープなどに貼り付けて捕殺します。
また、黄色い粘着シートを株元近くに設置するのも有効です。
ウンカを含む多くの害虫は黄色に誘引される習性があるため、シートに面白いように捕獲できることがあります。
家庭菜園レベルであれば、こまめに植物を観察し、見つけ次第捕殺する地道な作業が効果的です。
二度と発生させないためのウンカ虫の総合的な予防策
ウンカ虫の被害を最小限に抑えるためには、発生してからの駆除だけでなく、そもそも発生させない、増やさないための「予防」が最も重要です。
農薬だけに頼るのではなく、栽培環境そのものを見直す「総合的病害虫管理(IPM: Integrated Pest Management)」の考え方を取り入れ、複数の予防策を組み合わせることで、ウンカ虫に強い水田環境を構築しましょう。
ウンカ抵抗性品種の導入を検討する
ウンカ対策の最も効果的な手段の一つが、ウンカへの抵抗性を持つイネの品種を導入することです。
抵抗性品種とは、特定の種類のウンカが吸汁しにくい、または吸汁しても稲の生育への影響が少ない性質を持つように改良された品種を指します。
これにより、農薬の使用回数や量を大幅に削減でき、労力とコストの軽減につながります。
代表的なウンカ抵抗性品種には、トビイロウンカに強い「にじのきらめき」「つきあかり」や、セジロウンカとトビイロウンカの両方に抵抗性を持つ「あきだわら」などがあります。
ただし、抵抗性品種は特定のウンカ種にしか効果がなかったり、地域によっては抵抗性を持たない新たなウンカ(バイオタイプ)が発生して効果が薄れる可能性もあります。
また、食味や収量、地域の気候への適性も考慮する必要があります。
どの品種がご自身の圃場に適しているか、地域のJA(農業協同組合)や農業改良普及センターに相談し、最新の情報を得た上で導入を検討しましょう。
栽培管理の見直しで発生しにくい環境を作る
日々の栽培管理を少し見直すだけで、ウンカ虫が発生・増殖しにくい環境を作り出すことができます。
ウンカは高温多湿で風通しの悪い場所を好むため、稲の生育環境を健全に保つことが、何よりの予防策となります。
適切な株間で風通しを確保する
稲を密植すると、株元に日光が届かず、湿度が高くジメジメした環境になります。
これはウンカにとって絶好の隠れ家であり、繁殖の温床となります。
また、密集していると農薬を散布しても株元まで薬液が届きにくくなり、駆除効果が低下する原因にもなります。
適切な株間(条間・株間)を確保し、圃場全体の風通しを良くすることが重要です。
これにより、株元の湿度が下がり、ウンカの生息に適さない環境を作ることができます。
地域の推奨する栽植密度を基準に、ご自身の圃場の状況に合わせて調整しましょう。
窒素肥料の施肥設計を最適化する
窒素肥料の過剰な施用は、稲を軟弱に育て、葉が過剰に繁茂する「過繁茂」の状態を引き起こします。
このような稲はウンカにとって吸汁しやすく、格好の餌食となります。
また、過繁茂になった株元は日陰となり、風通しも悪化するため、ウンカの増殖をさらに助長してしまいます。
土壌診断の結果に基づいて適正な施肥量を守り、特にウンカの発生時期と重なる穂肥(追肥)の量やタイミングは慎重に検討する必要があります。
地域の施肥基準を参考に、稲の生育状況をよく観察しながら、適切な施肥管理を心がけましょう。
水管理を徹底し初期の増殖を防ぐ
水管理もウンカの発生に大きく関わります。
特に、イネの無効分けつ(収穫に結びつかない茎)の発生を抑制し、根を健全に育てるために行う「中干し」は、ウンカ対策としても非常に有効です。
中干しによって一時的に水田の水を抜いて土壌を乾かすことで、株元の環境が改善され、ウンカの初期の増殖を抑制する効果が期待できます。
適切な時期(一般的には有効分けつが確保できた後)に、土の表面に軽くひびが入る程度までしっかりと中干しを行いましょう。
ただし、干しすぎは稲の生育に悪影響を及ぼす可能性もあるため、天候や土壌の状態を見ながら適切に実施することが大切です。
早期発見が鍵 定期的な圃場観察の重要性
ウンカは海外から飛来するため、どれだけ予防策を講じても発生を完全に防ぐことは困難です。
そこで重要になるのが、圃場を定期的に観察し、ウンカの発生をいち早く察知する「早期発見」です。
発生初期の数が少ないうちに対処できれば、被害を最小限に食い止めることができます。
特に、梅雨明け後の高温が続く時期は、ウンカの飛来と増殖が活発になります。
この時期は週に2〜3回など、観察の頻度を上げましょう。観察する際は、稲の株元をかき分けて、成虫や幼虫がいないか直接確認します。
特に、田んぼの縁や風下になりやすい場所はウンカが集まりやすいため、重点的にチェックしてください。
また、ウンカの排泄物が原因で発生する「すす病」による株元の黒ずみや、吸汁による葉の黄化なども発生のサインです。
地域の農業機関が発表する病害虫発生予察情報をこまめに確認することも非常に重要です。
これにより、ウンカの飛来時期や発生状況を予測し、より警戒を強めることができます。
発生を確認した場合は、速やかに次の駆除対策に移れるよう、あらかじめ準備しておきましょう。
まとめ
ウンカ虫はイネに甚大な被害を及ぼすため、早期の対策が不可欠です。
発生した場合は、箱処理剤や粒剤、茎葉散布剤といった農薬を適切な時期に使用することが効果的です。
しかし、最も重要なのは、発生を未然に防ぐ総合的な予防策です。
海外からの飛来という主な原因に加え、密植や窒素過多も発生を助長します。
抵抗性品種の導入や適切な栽培管理、日々の圃場観察を組み合わせ、安定した収穫を目指しましょう。